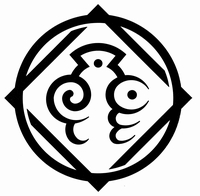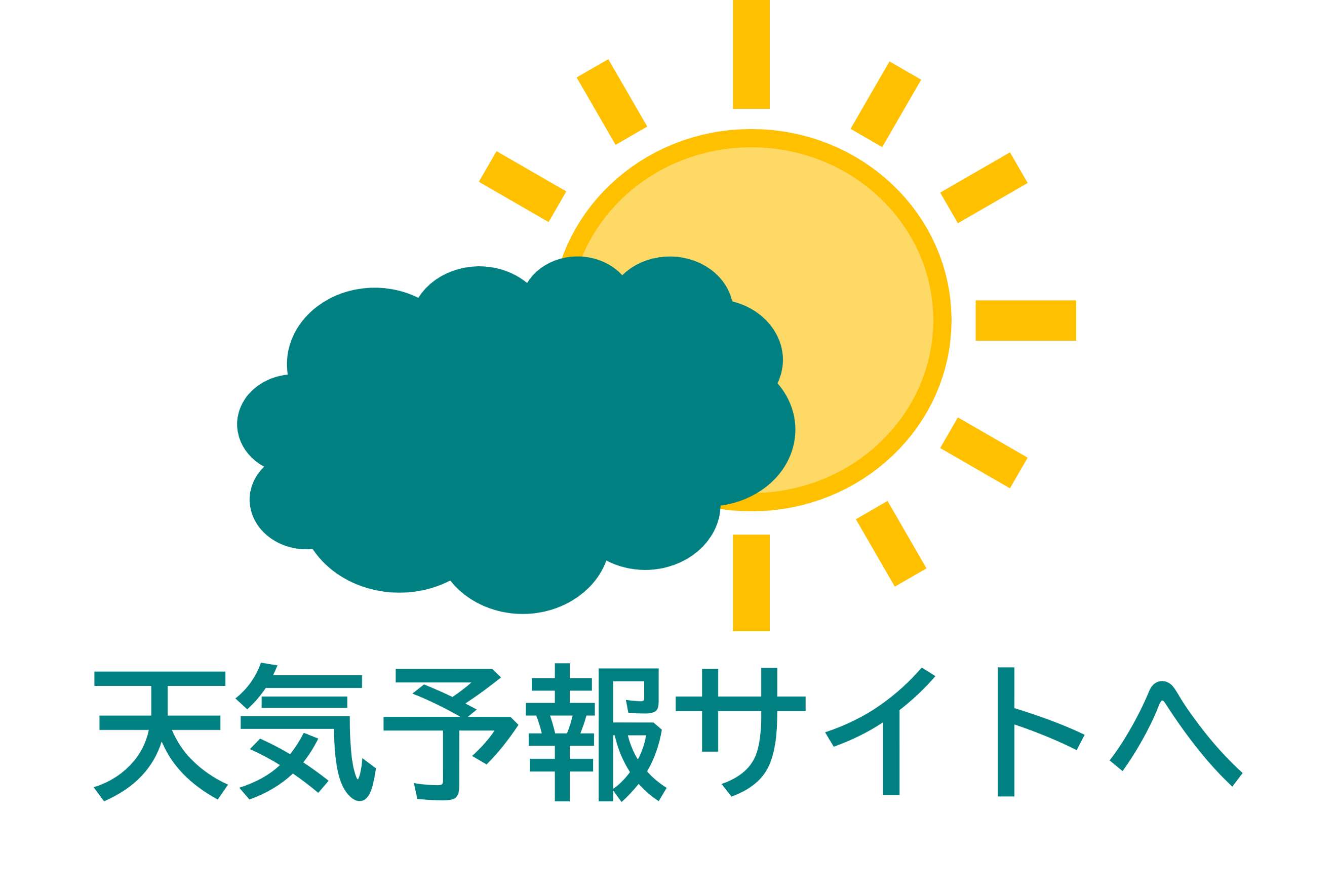リンク・用語集
防災関連リンク
災害・防災情報関係
- 鳥取市公式ウェブサイト
- とりみちinfo:鳥取市
- 鳥取県土砂災害警戒情報
- 鳥取県土砂災害警戒区域・AR表示機能「みえるでござる」
- 鳥取県防災ポータルサイト
- 鳥取県ため池監視システム
- 川の防災情報:国土交通省
- 被災者支援制度一覧
電気
通信
交通
- 列車運行情報:JR西日本
- バス等運行情報:日本交通
- バス等運行情報:日ノ丸自動車
- 飛行機運行情報:鳥取砂丘コナン空港
鳥取市の災害に関する計画等
計画関係
- 鳥取市地域防災計画
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、防災活動を総合的かつ計画的に推進し、市域及び市民の生命・財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するのに必要な防災に関する基本的事項を総合的に定めたもの。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1426137956677/index.html
- 鳥取市国民保護計画
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第35条に基づき、武力攻撃や大規模なテロなどの緊急事態から国民の生命、身体、財産を保護するため、国および地方公共団体、そのほかの機関などが相互に協力して、的確かつ迅速な措置を実施する責務を明確にしたもの。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1546824427375/index.html
- 鳥取市災害時業務継続計画
- 災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務(非常時優先業務)を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定めたもの。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1652922576142/index.html
- 鳥取市災害時受援計画
- 災害時、被災市町村では、短期間に膨大な災害対応業務が発生するため、外部からの応援が不可欠である。そのため、応援職員等を迅速、的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための体制と受援対象業務を明確にしたもの。
- 鳥取市水防計画
- 水防法第33条第1項の規定に基づき、鳥取市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、鳥取市の地域にかかる河川、湖沼又は海岸の洪水、津波又は高潮の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。
- 鳥取市国土強靱化地域計画
- 大規模自然災害に対する健康診断となる「脆弱性評価」を踏まえ、県や国など関係者相互の連携のもと、鳥取市における国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針を定めたもの。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1711518604129/index.html
- 鳥取市積雪対応指針
- 道路交通網の大規模障害、公共交通機関の運休、停電など、市民生活に大きな影響をもたらす大雪被害を最小限に抑えるため、市の組織体制、除雪対策、国・県等の関係機関との連携、雪への備えなどの推進等をまとめたもの。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1513234953149/index.html
制度・マニュアル
- 鳥取市避難行動要支援者支援制度
- 災害時に一人暮らしの高齢者や障がいのある方などで自力で避難できない人を、自治会町内会、自主防災会など地域で支援する(互助・共助)ことで、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりをめざすための制度。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1332828162808/index.html
- 鳥取市避難所運営マニュアル
- 大規模な災害が発生した場合に、住民(地域の自主防災会を中心とした組織)、施設管理者、市の3者が協力して、避難所の開設から運営までを円滑に実施することを目的として作成したもの。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1576492113945/index.html
避難行動に関すること
警戒レベルと避難情報
- 警戒レベル相当情報
- 国土交通省、気象庁、都道府県等が発表する河川や雨などに関する防災気象情報のうち、避難情報等の発令判断で活用を想定する情報について、危険度を5段階で整理したもの。警戒レベルとの関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促すことを目的とする。
- 警戒レベル
- 市町村が発表する避難情報など、住民に対する「行動を促す情報」の危険度を5段階に整理したもの。これに合わせて「住民がとるべき情報」が設定されており、住民等の避難行動指針が設定されている。
- 警戒レベル1・2は、気象庁が発表する防災気象情報。
- 警戒レベル3・4・5は、市町村が発令する避難情報。
- 「警戒レベル」と「警戒レベル相当情報」の違い
- 「警戒レベル」は、市町村や気象庁が発令する避難情報等に付される数字で、災害発生のおそれの高まりに応じて住民の方々がとるべき行動と当該行動を住民の方々に促す情報とを関連づけるもの。
- 一方、「警戒レベル相当情報」は、国土交通省、気象庁、都道府県等が発表する防災気象情報に付されるもので、住民が主体的に避難行動等を判断するための参考となる状況情報。
- 市町村は防災気象情報のほか、様々な情報を踏まえ避難情報を発令するため、同じレベル相当の防災気象情報と避難情報の出るタイミングが必ずしも同時になるわけではない。
- https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201906/2.html
- 警戒レベル1
- 災害への心構えを高めることが必要とされる段階。
- 最新の防災気象情報等への留意が推奨される。
- 【対象情報】
- 早期注意情報(警報級の可能性:[高]又は[中]が予想されている場合)
- 警戒レベル2
- 避難行動の確認が必要とされる段階。
- ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路の確認が推奨される。
- 【対象情報】
- 大雨注意報
- 洪水注意報
- 高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの)
- 警戒レベル2相当情報
- 避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。
- 【対象情報】
- キキクル「注意」(黄)
- 氾濫注意情報
- 警戒レベル3「高齢者等避難」
- ●発令される状況:災害のおそれあり
- ●居住者等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難
- ・高齢者等※は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
- ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者
- ・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。
- 警戒レベル3相当情報
- 警戒レベル3高齢者等避難を発令する目安となる情報。
- 災害が想定されている区域等では、自治体からの高齢者等避難の発令に留意するとともに、高齢者等以外の方も普段の行動を見合わせたり、避難の準備や自発的な避難の検討をすることが推奨される。
- 【対象情報】
- 大雨警報(土砂災害)
- 洪水警報
- キキクル「警戒」(赤)
- 氾濫警戒情報
- 高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの)
- 警戒レベル4「避難指示」
- ●発令される状況:災害のおそれ高い
- ●居住者等がとるべき行動:危険な場所から全員避難
- ・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。
- 警戒レベル4相当情報
- 警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報。
- 災害が想定されている区域等では、自治体からの避難指示の発令に留意するとともに、避難指示が発令されていなくてもキキクルや河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断をすることが推奨される。
- 【対象情報】
- 土砂災害警戒情報
- キキクル「危険」(紫)
- 氾濫危険情報
- 高潮特別警報
- 高潮警報
- 警戒レベル5「緊急安全確保」
- ●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)
- ●居住者等がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!
- ・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。
- 警戒レベル5相当情報
- 警戒レベル5緊急安全確保を発令する判断材料となる情報。
- 何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況となっています。
- 命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保が必要。
- 【対象情報】
- 大雨特別警報
- 氾濫発生情報
- キキクル「災害切迫」(黒)
避難行動
- 避難
- 「難」を「避」けることであり、小中学校や公民館等の指定緊急避難場所に行くことだけが避難ではなく、それ以外にも安全な親戚・知人宅やホテル・旅館等の避難先への立退き避難、自らの判断で屋内安全確保をする等、様々な避難行動がある。
- 水平避難
- 自らが居る建物から離れ避難すること。
- 垂直避難
- 浸水から身を守るため上の方に避難すること。
- 在宅避難
- 災害時において自宅に倒壊や焼損、浸水、流出の危険性がない場合に、そのまま自宅で生活を送る方法。
- 旅館・ホテル避難
- 避難所での避難生活が長期にわたる場合や、あらかじめ指定した指定避難所だけでは避難所が不足する場合等において、ホテル・旅館等を避難所として活用すること。
- 立退き避難
- 自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれがあることから、その場を離れ、災害リスクのある区域等の外側など安全な場所に移動すること。
- ●当該行動が関係する災害: 洪水等、土砂災害、高潮、津波
- ●当該行動をとるタイミング:高齢者等避難、避難指示の発令時
- ●当該行動は、リードタイムを確保できる場合にとるべき避難行動
- 屋内安全確保
- 洪水や高潮等の災害リスクのある区域等にある自宅等で、浸水深より高い位置にある部屋に移動したり、高階層に留まる(待避する)ことで、身の安全を確保すること。
- ただし、「屋内安全確保」を行うためには少なくとも以下の条件が満たされている必要があり、居住者等が自ら確認・判断する必要がある。
- 1.自宅等が家屋倒壊等氾濫想定区域外にあること
- 2.自宅等に、想定浸水深より高い(浸水しない)位置にある居室があること
- 3.自宅等周辺の水がひくまで我慢でき、水・食糧などの備えが十分にあること
- ※土砂災害及び津波については、自宅等が外力により倒壊するおそれがあるため、立退き避難を推奨。
- 緊急安全確保
- 「立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難し遅れ、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある場合、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること。
- ただし、本行動は、災害が既に発生・切迫している状況において避難し遅れた居住者等がとる次善の行動であるため、本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らず、このような状況に至る前の警戒レベル3高齢者等避難や警戒レベル4避難指示が発令されたタイミングで避難する必要がある。
- 災害が切迫する
- 災害が発生直前、又は未確認だが既に発生している蓋然性が高い状況
- リードタイム
- リードタイムとは、指定緊急避難場所等への立退き避難に要する時間のこと。
- リードタイムを確保可能であれば、基本的には、災害が発生する前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を安全に完了することが期待できる。
災害・現象
風水害に関すること
- 風水害(ふうすいがい)
- 強風と大雨および高潮、波浪により起こる災害の総称。
- 水害(すいがい)
- 大雨や強雨、あるいは融雪水が原因となって起こる災害の総称。
- 洪水
- 河川の水位や流量が異常に増大することにより、平常の河道から河川敷内に水があふれること、及び、堤防等から河川敷の外側に水があふれること。
- 氾濫(はんらん)
- 河川の水がいっぱいになってあふれ出ること。
- 外水氾濫(がいすいはんらん)
- 河川の水位が上昇し、堤防を越えたり破堤するなどして堤防から水があふれ出ること。
- 内水氾濫(ないすいはんらん)
- 河川の水位の上昇や流域内の多量の降雨などにより、河川外における住宅地などの排水が困難となり浸水すること。
- 土砂災害
- 山や崖の土砂が崩れたり、崩れた土砂が雨水や川の水と混じって流れてきたりすることによって、家や道路や田畑が土砂で埋まったり、人命が奪われたりする災害。
- https://www.sabopc.or.jp/library/sediment_disaster/
- 土石流(どせきりゅう)
- 山腹、谷底にある土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象。
- 地すべり
- 斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象。
- 崖崩れ(がけくずれ)
- 降雨時に地中にしみ込んだ水分により不安定化した斜面が急激に崩れ落ちる現象。
- 豪雨
- 著しい災害が発生した顕著な大雨現象。
- 集中豪雨
- 同じような場所で数時間にわたり強く降り、100mmから数百mmの雨量をもたらす雨。
- 線状降水帯(せんじょうこうすいたい)
- 次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域。
- ※「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する気象情報」は次の基準により発表する。
- 現在、10分先、20分先、30分先のいずれかにおいて、以下の基準をすべて満たす場合に発表。
- 1. 前3時間積算降水量(5kmメッシュ)が100mm以上の分布域の面積が500km2以上
- 2. 1.の形状が線状(長軸・短軸比2.5以上)
- 3. 1.の領域内の前3時間積算降水量最大値が150mm以上
- 4. 1.の領域内の土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)において土砂災害警戒情報の基準を超過(かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合8割以上)又は洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)において警報基準を大きく超過した基準を超過
- 局地的大雨:ゲリラ豪雨
- 急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十mm程度の雨量をもたらす雨。「局地的な大雨」とも言う。
- 熱帯低気圧
- 1)熱帯または亜熱帯地方に発生する低気圧の総称で、風の弱いものから台風やハリケーンのように強いものまである。
- 2)気象情報等で「熱帯低気圧」を用いる場合は、台風に満たない、低気圧域内の最大風速がおよそ17m/s(34ノット、風力8)未満のものを指す。
- 台風
- 北西太平洋または南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のもの。
- 予報円
- 台風や暴風域を伴う低気圧の中心が予報時刻に到達すると予想される範囲を円で表したもの。
- 強風域
- 台風や発達した低気圧の周辺で、平均風速が15m/s以上の風が吹いているか、地形の影響などがない場合に、吹く可能性のある領域。通常、その範囲を円で示す。
- 暴風域
- 台風の周辺で、平均風速が25m/s以上の風が吹いているか、地形の影響などがない場合に、吹く可能性のある領域。通常、その範囲を円で示す。
- 暴風警戒域
- 台風の中心が予報円内に進んだときに、暴風域に入るおそれのある領域。
- 台風の大きさ
- 台風に伴う風速15m/s以上の領域の半径を基準にして次のように決める。風速15m/s以上の半径が非対称の場合は、その平均値をとる。
- 【大きさの表現と風速15m/sの半径】
- 表現しない場合:500km未満
- 大型(大きい) :500km以上800km未満
- 超大型(非常に大きい):800km以上
- 台風の強さ
- 台風の最大風速を基準にして次のように決める。
- 【強さの表現と最大風速】
- 表現しない場合:33m/s(64ノット)未満
- 強い:33m/s(64ノット)以上44m/s(85ノット)未満
- 非常に強い:44m/s(85ノット)以上54m/s(105ノット)未満
- 猛烈な:54m/s(105ノット)以上
- 高潮
- 台風や発達した低気圧が通過するとき、潮位が大きく上昇すること。
- 偏西風
- 極を中心にして西から東に向かって吹く地球規模の帯状風。
- モンスーン
- 季節的交替する卓越風系、すなわち季節風を意味する。 広い意味では、この季節風伴う雨季も含めて、モンスーンと定義される。
- エルニーニョ現象
- 東部太平洋赤道域で2~7年おきに海面水温が平年より1~2℃、ときには2~5℃も高くなり、半年から1年半程度続く現象。この影響は地球全体に及び、世界各地に異常気象を引き起こす傾向がある。
- ラニーニャ現象
- エルニーニョ現象とは逆に、東部太平洋赤道域の海面水温が平年より低くなる現象。
- 前線
- 寒気団と暖気団との境界線で、風向、風速の変化や降水を伴っていることが多い。前線はその動きと構造によって温暖、寒冷、閉塞、停滞の4種類に分けられる。
- 梅雨前線(ばいうぜんせん)
- 春から盛夏への季節の移行期に、日本から中国大陸付近に出現する停滞前線で、一般的には、南北振動を繰り返しながら沖縄地方から東北地方へゆっくり北上する。
- 秋雨前線(あきさめぜんせん)
- 夏から秋への季節の移行期に、日本付近に出現して、長雨をもたらす停滞前線。
- 日本海寒帯気団収束帯:JPCZ
- 冬に日本海で、寒気の吹き出しに伴って形成される。水平スケールが1000km程度の収束帯。この収束帯に伴う帯状の雲域を、「帯状雲」と呼ぶ。強い冬型の気圧配置や上空の寒気が流れ込む時に、この収束帯付近で対流雲が組織的に発達し、本州日本海側の地域では局地的に大雪となることがある。Japan sea Polar air mass Convergence Zone
地震に関すること
- 地震
- 地下の岩盤が周囲から押される、もしくは引っ張られることによって、ある面を境として岩盤が急激にずれる現象。
- 震度
- ある場所における地震の揺れの強弱の程度。気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値。
- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html
- マグニチュード
- マグニチュードは、地震そのものの大きさ(エネルギー)を表す。
- マグニチュードは1大きくなると約32倍大きくなり、2大きくなると、1000倍になる。 つまり、マグニチュード8クラスの地震は、マグニチュード6クラスの地震の1000個分のエネルギーがあることになる。
- 長周期地震動
- 大きな地震で生じる、周期(揺れが1往復するのにかかる時間)が長い大きな揺れのこと。
- 震源
- 地震発生の際に地球内部の岩石の破壊が開始した地点。
- 震央
- 震源の真上にあたる地表の地点。
- 本震
- 最初の地震(最も大きな地震)。
- 余震
- 本震に続く小さな地震。本震の直後には多く発生し、時間とともに減少するが、一時的に余震が活発化することもある。また、規模は、本震のマグニチュードより1程度以上小さいことが多いが、本震に近い規模の地震が発生することもある。
- P波
- 速いスピード(秒速約7km/s)で伝わる地震波。
- S波
- P波と比較してスピードは遅い(秒速約4km/s)が揺れは強い地震波。
- 地盤沈下
- 粘土層の間にある、礫・砂層などの間隙に閉じ込められた地下水を過剰揚水することにより、粘土層からの間隙水が絞りだされ、その粘土層が収縮することにより地面が沈む現象。
- 液状化現象
- ゆるく堆積した砂の地盤に強い地震動が加わると、地層自体が液体状になる現象。
- 地殻変動
- 地球の表面を構成する地殻に、さまざまな力が加わり、生じた変動を地表面の変形として捉えたもの。
- プレート
- 地球表面を覆う岩石の層のこと。
- 断層
- プレートの中で強度が弱い場所。
- 鹿野・吉岡断層(しかの-よしおか)
- 鹿野町から吉岡温泉町を経て、滝山にかけて分布する活断層。長さは約26kmで、概ね東西方向に延びている。鹿野-吉岡断層は横ずれを主体とする断層。
- 鹿野-吉岡断層の断層面の長さは、地表で確認される断層長さと同じ約26kmであると推定され、断層面の傾斜はほぼ鉛直と推定される。
- https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_katsudanso/shikano-yoshioka/
- 雨滝-釜戸断層(あめだき-かまと)
- 岩美郡岩美町から国府町にかけて分布する活断層。長さは約13kmで、概ね北西-南東方向に延びている。雨滝-釜戸断層は左横ずれを主体とし、東側隆起の成分を伴う断層。
- 雨滝-釜戸断層の断層面の長さは、不明で、断層面の傾斜は、高角(北東傾斜)と推定される。
- https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_katsudanso/amedaki-kamato/
- F55断層
- 鳥取の海岸線に並行するように、概ね海岸から10~20kmほど沖合を3つの区間に分かれて東西に走っている断層。断層の幅が 16km 程度で北傾斜構造を取っており、東西に圧縮する力によって断層沿いに水平へ動く横ずれ断層。
- ここで規模の大きな地震が起きた場合、水平の動きだけではなくある程度の上下方向の動きも発生すると考えられ、それによって鳥取県沖の海底が上下に動いて津波が発生する可能性が高い。
- 山崎断層帯
- 岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する活断層帯。
- 南海トラフ地震
- 駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100~150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震。
- 科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震(南海トラフ巨大地震)が発生した場合、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があるほか、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定される。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
- 房総半島東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝と千島海溝の地殻の境界等を震源とする地震。
- 30年以内に地震が発生する確率は60%など様々なケースがある。最大で20mを超える大きな津波が襲来する恐れがある。
- 首都直下地震
- 首都及びその周辺地域の直下で発生するマグニチュード7クラスの地震及び相模トラフ(相模湾から房総半島南東沖までの海底の溝)沿い等で発生するマグニチュード8クラスの海溝型地震のこと。
- 30年以内に70%の確率で起きるとされるマグニチュード7クラスの首都直下地震が都心南部直下で発生した場合には、最悪の場合、死者が約2万3,000人、経済被害が約95兆円に上るとの想定が発表されている。
- 中部圏・近畿圏直下地震
- 過去の事例によると、西日本においては、活断層の地震により甚大な被害がもたらされた事例や、南海トラフ地震の前後に活動が活発化した事例があり、府県を越えて市街地が広がっている中部圏・近畿圏で大規模地震が発生した場合の被害は甚大かつ広域にわたると想定される。
- 津波
- 津(港)に押し寄せる、異常に大きな波。津波は、海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起・沈降や海底における地滑りなどにより、その周辺の海水が上下に変動することによって引き起こされる。
- 津波高
- 津波がない場合の潮位(平常潮位)から、津波によって海面が上昇した高さ(極値)の差。観測値からは、第1波の津波の高さ、第2波の津波の高さなど、複数の高さが求められる。
- 遡上高(そじょうだか):痕跡高、浸水高
- 津波がない場合の潮位(平常潮位)から津波痕跡までの高さ。
- 河川津波
- 河川を遡上した津波をいう。
- 引き潮
- 海面がしだいに下降し、海岸線が沖に退くこと。
防災に関する情報
防災気象情報
- 気象注意報
- 災害が発生するおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報。気象庁で発表する16種類の情報。
- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
- 大雨注意報
- 大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続する。
- 洪水注意報
- 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 対象となる洪水災害として、河川の増水及び堤防の損傷、並びにこれらによる浸水害があげられる。
- 大雪注意報
- 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 強風注意報
- 強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 風雪注意報
- 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 強風による災害のおそれに加え、強風で雪が舞って視界が遮られることによる災害のおそれについても注意を呼びかける。ただし「大雪+強風」の意味ではなく、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときには大雪注意報を発表する。
- 波浪注意報
- 高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 高潮注意報
- 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 雷注意報
- 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 濃霧注意報
- 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 対象となる災害として、濃い霧により見通しが悪くなることによる交通障害等の災害があげられる。
- 乾燥注意報
- 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 具体的には、大気の乾燥により火災・延焼等が発生する危険が大きい気象条件を予想した場合に発表する。
- なだれ注意報
- なだれによる災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 山などの斜面に積もった雪が崩落することによる人や建物の被害が発生するおそれがあると予想したときに発表する。
- 着氷注意報
- 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 具体的には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通信線・送電線の断線、船体着氷による転覆・沈没等の被害が発生するおそれのあるときに発表する。
- 着雪注意報
- 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 具体的には、雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等の倒壊等の被害が発生する(気温0℃付近で発生しやすい)おそれのあるときに発表する。
- 融雪注意報
- 融雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 具体的には、積雪が融解することによる土砂災害や浸水害が発生するおそれがあるときに発表する。
- 霜注意報
- 霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。具体的には、春・秋に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果実の被害が発生するおそれのあるときに発表する。
- 低温注意報
- 低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 具体的には、低温による農作物の被害(冷夏の場合も含む)や水道管の凍結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるときに発表する。
- 気象警報
- 重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報。気象庁で発表する7種類の情報。
- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
- 大雨警報
- 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表。 特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨警報(土砂災害)」、「大雨警報(浸水害)」又は「大雨警報(土砂災害、浸水害)」のように発表する。雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続する。
- 洪水警報
- 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 対象となる重大な洪水災害として、河川の増水・氾濫及び堤防の損傷・決壊、並びにこれらによる重大な浸水害があげられる。
- 大雪警報
- 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 暴風警報
- 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 暴風雪警報
- 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 暴風による重大な災害のおそれに加え、暴風で雪が舞って視界が遮られることによる重大な災害のおそれについても警戒を呼びかける。ただし「大雪+暴風」の意味ではなく、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときには大雪警報を発表する。
- 波浪警報
- 高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 高潮警報
- 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。
- 特別警報
- 警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく高まっている場合、特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかける。気象庁で発表する6種類の情報。
- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html
- 大雨特別警報
- 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表。
- 特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨特別警報(土砂災害)」、「大雨特別警報(浸水害)」又は「大雨特別警報(土砂災害、浸水害)」のように発表する。
- 大雪特別警報
- 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表。
- 暴風特別警報
- 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合に発表。
- 暴風雪特別警報
- 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合に発表。
- 波浪特別警報
- 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合に発表。
- 高潮特別警報
- 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合に発表。
- 警報・注意報発表基準一覧表
- 気象等に関する特別警報の発表基準
- 土砂災害警戒情報
- 大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まったときに、市町村長が避難指示の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難の判断の参考となるよう、対象となる市町村を特定して都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報。
- https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=310000&lang=ja
- 早期注意情報(警報級の可能性)
- 警報級の現象が5日先までに予想されるときに、その可能性を高さに応じて[高]、[中]の2段階で伝える情報。
- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/prob_warning.html
- 全般気象情報
- 全国を対象とする気象情報。
- 地方気象情報
- 全国を11に分けた地方予報区を対象とする気象情報。
- 府県気象情報
- 都道府県を対象とする気象情報。
- 顕著な大雨に関する気象情報
- 大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報。
- この情報は警戒レベル相当情報を補足するもの。警戒レベル4相当以上の状況で発表する。
- 記録的短時間大雨情報
- 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨量計による観測)したり、解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析:解析雨量)したりしたときに発表。
- この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることを知らせる。
- 全般台風情報
- 台風が発生した時や、台風や熱帯低気圧※が日本に影響を及ぼすおそれがある時、既に影響を及ぼしている時に発表。
- 早期天候情報
- 情報発表日の6日後から14日後までを対象として、 5日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が30%以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30%以上と見込まれる場合に発表。
- https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/
- 竜巻注意情報
- 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバーストなどの激しい突風(以下「竜巻等」)に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報を補足する情報として発表。
- https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#8/35.049/133.667/&element=tornado&contents=information
指定河川洪水予報
- 指定河川洪水予報
- 河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、気象庁は国土交通省または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報。
- 国土交通省と共同で行う指定河川洪水予報
- 2つ以上の都府県にわたる河川または流域面積の大きい河川で、洪水によって重大な損害が生ずるおそれのあるものについて、国土交通大臣が指定する河川。
- 都道府県と共同で行う指定河川洪水予報
- 洪水によって相当の被害が発生するおそれのあるものについて、気象庁と協議して都道府県知事が指定する河川。
- 対象河川:千代川、袋川・新袋川
- 氾濫注意情報(はんらんちゅういじょうほう)
- 避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。
- ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路の確認を推奨。
- 氾濫警戒情報(はんらんけいかいじょうほう)
- 警戒レベル3高齢者等避難を発令する目安となる情報。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3に相当。
- 災害が想定されている区域等では、自治体からの高齢者等避難の発令に留意するとともに、高齢者等以外の方も避難の準備をしたり自ら避難の判断を推奨。
- 氾濫危険情報(はんらんきけんじょうほう)
- 警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4に相当。
- 災害が想定されている区域等では、自治体からの避難指示の発令に留意するとともに、避難指示が発令されていなくても自ら避難の判断を推奨。
- 氾濫発生情報(はんらんはっせいじょうほう)
- 警戒レベル5緊急安全確保を発令する判断材料となる情報。災害がすでに発生していることを示す警戒レベル5に相当。
- 災害がすでに発生している状況となっており、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保すること。
水位周知
- 水位周知河川
- 洪水により重大な損害を生ずるおそれのある中小河川。
- 対象河川:袋川、大路川、野坂川、八東川
- 水防団待機水位(すいぼうだんたいきすいい)
- 水防団が待機する水位。
- 氾濫注意水位(はんらんちゅういすいい)
- 増水時に災害が起こるおそれがある水位。河川の氾濫の発生に注意を求めるレベルに相当する。
- 避難判断水位
- 住民に対し氾濫発生の危険性についての注意喚起を開始する水位。市町村長の高齢者等避難の発令判断の目安。
- 氾濫危険水位(はんらんきけんすいい)
- 洪水、内水氾濫により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こるおそれがある水位。市町村長の避難情報の発令判断の目安。
水防警報
- 水防警報
- 河川が所定の水位に達した際に、防災機関(水防団や消防機関など)の出動の指針とするために発表。
- https://city.river.go.jp/kawabou/reference/index06.html
- 水防団
- 災害発生時の洪水や高潮等の被害を最小限にくい止めるための活動のほか,水防月間や水防訓練その他の機会を通じて広く地域住民等に対し水防の重要性の周知や水防思想の高揚のための啓発,訓練及び危険箇所の巡回・点検等の活動を行う水防管理団体。
- 平常時は各自の職業に従事しながら,非常時には水防管理者の指示により参集し水防活動に従事している。
- 待機
- 1.増水あるいは水位の再上昇等が予想される場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告するもの。
- 2.水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減らしてもさしつかえないが、水防活動をやめることはできない旨を警告するもの。
- 気象情報、警報等及び河川状況により、必要と認める時に発表する。
- 準備
- 水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水閘門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。
- 雨量、水位、流量とその他の河川状況により必要と認める時に発表する。
- 出動
- 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。
- 洪水注意報等により、または、水位、流量その他の河川状況により、氾濫注意水位を超えるおそれがある時に発表する。
- 指示
- 水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示するとともに、越水、漏水、法崩、亀裂その他河川状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するもの。
- 洪水警報等により、または、既に氾濫注意水位を超え、災害のおこるおそれがある時に発表する。
- 解除
- 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。
- 氾濫注意水位以下に下降したとき、または、氾濫注意水位以上であっても水防作業を必要とする河川状況が解消したと認める時に発表する。
地震に関する情報
- 緊急地震速報
- 計算した地震の規模や予測震度等が発表基準に達した場合には、それぞれの基準に応じて緊急地震速報の警報と予報を発表。
- ただし、解析や伝達に一定の時間(数秒程度)がかかるため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合などにおいて、震源に近い場所への緊急地震速報の提供が強い揺れの到達に原理的に間に合わないことに注意が必要。
- 震度速報
- 地震発生約1分半後に、震度3以上を観測した地域名(全国を188地域に区分)と地震の揺れの検知時刻を速報。
- 震源に関する情報
- 震度3以上で、「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加して、地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。津波警報または注意報を発表した場合は発表しない。
- 震源・震度情報
- 地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)、震度1以上を観測した地点と観測した震度を発表。それに加えて、震度3以上を観測した地域名と市町村毎の観測した震度を発表。震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村・地点名を発表。
- 長周期地震動に関する観測情報
- 地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表。(地震発生から10分後程度で1回発表)
- 長周期地震動階級
- 固有周期が1~2秒から7~8秒程度の揺れが生じる高層ビル内における、地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度から4つの段階に区分した揺れの大きさの指標。
- https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/ltpgm_explain/about_level.html
南海トラフ地震に関連する情報
- 南海トラフ地震臨時情報
- ・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合
- ・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合
- 調査中
- 下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催する場合に発表。
- ・監視領域内(下図黄枠部)でマグニチュード6.8以上の地震が発生
- ・1カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界(下図赤枠部)で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測
- ・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測
- 下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催する場合に発表。
- 巨大地震警戒
- 想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード8.0以上の地震が発生したと評価した場合の情報
- 巨大地震注意
- ・監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震 2が発生したと評価した場合(巨大地震警戒に該当する場合は除く)の情報
- ・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合の情報
- 調査終了
- (巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合の情報
- 南海トラフ地震関連解説情報
- ・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合の情報。
- ・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合(ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く)の情報。
- ※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。
ハザードマップ
防災マップ
- 鳥取市総合防災マップ
- 洪水、土砂災害、津波の危険地域などの情報を住民の皆様に分かりやすく提供することで、防災意識の向上や災害時に向けての事前の備えを心がけていただくことを目的に市が作成したマップ。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1584067921065/index.html
- 地区防災マップ
- 地区自主防災会連絡協議会など地域主体で作成する防災マップ。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1680243112953/simple/zyoseiitirannhyou.pdf
洪水・浸水
- 洪水浸水想定区域計画規模:L1
- 10~100年に1回程度の降雨規模を想定した洪水浸水想定区域。100年毎に1回発生する周期的な降雨ではなく、1年の間に発生する確率が 1/100(1%)以下の降雨。
- 洪水浸水想定区域想定最大:L2
- 1000年に1回程度の降雨規模を想定した洪水浸水想定区域。1000年毎に1回発生する周期的な降雨ではなく、1年の間に発生する確率が 1/1000(0.2%)以下の降雨。毎年の発生確率は小さいが、規模の大きな降雨であることを示している。
- 家屋倒壊等氾濫想定区域河岸浸食
- 河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により河岸の侵食幅を予測した家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域を表示したもの。
- 家屋倒壊等氾濫想定区域氾濫流
- 河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により河川が氾濫した場合の氾濫流の状況をシミュレーションにより予測した家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域を表示したもの。
- 浸水継続時間
- 河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により河川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測した浸水継続時間を表示したもの。
- ダム下流部浸水想定図
- 想定し得る最大規模の降雨によりダム下流河川が氾濫した場合に浸水が想定される範囲及び浸水深、浸水の継続時間、家屋の倒壊・流出をもたらすような氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される範囲を表示したもの。
- 内水浸水想定区域
- 指定時点の鳥取市(下水道計画区域)の地形情報や下水道の整備状況(雨水管、排水路、ポンプ施設など)、放流先の河川の情報を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う雨水出水により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションし、大雨時に下水道や水路など雨水を排除する施設からの浸水が想定される区域や浸水する深さの情報をまとめたもの。
土砂災害
- 土砂災害警戒区域
- 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。
- 土砂災害特別警戒区域
- 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。
防災関係組織等
鳥取市
- 鳥取市防災会議
- 鳥取市が、災害対策基本法第14条の規定に基づき設置し、地域防災計画に基づく防災対策の推進及び市町村・防災関係機関との連絡調整を行う会議。
- 鳥取市国民保護協議会
- 鳥取市において、国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会。
- 災害対策本部
- 災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、地域防災計画の定めるところにより設置する組織。
- 災害対策本部は、次の事務を行い、必要に応じて、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努める。
- ・災害に関する情報収集
- ・災害予防および災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針作成と実施
- 災害警戒本部
- 気象等に関する警報等の発表その他の災害が発生するおそれがあり、情報の収集・連絡体制の確立等速やかな初動態勢を確保するため必要があると危機管理部長が認めた場合は、市災害警戒本部を危機管理課に設置する。
消防団
- 消防団
- 消火活動のみならず、地震や風水害等多数の動員を必要とする大規模災害時の救助救出活動、避難誘導、災害防御活動など非常に重要な役割を果たしている。また、平常時においても、住民への防火指導、巡回広報、特別警戒、応急手当指導等、地域に密着した活動を展開しており、地域における消防力・防災力の向上、地域コミュニティの活性化に大きな役割を果たしている。
- 鳥取市消防団では、市域を7ブロックの管轄区域に分け、きめ細やかな消防業務を行っている
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/1247035952761/index.html
自主防災組織
- 自主防災組織
- 市民による「自らの地域は自らで守る」という自助・共助の意識に基づき、自主的に結成される地域の防災活動の中核となる組織で、災害対策基本法上では、「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」と規定されている。
- 鳥取市自主防災会連合会は、平時における防災知識の普及や意識の高揚、各種(初期消火、救出救護、避難等)訓練を実施するほか、災害時においては避難活動や避難行動要支援者への避難支援など、ほぼ市内全域に結成されている単位自主防災会が強い信念と連帯意識のもとに活動を行っている。(単位自主防災会結成率98%:2025年3月現在)
- また、市は、鳥取市自主防災会連合会補助金制度及び鳥取市自主防災会活動補助金制度により、自主防災組織の継続的かつ活発な活動の促進を図っている。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/1261009726030/index.html
- 防災リーダー
- 防災について十分な知識と経験を有する者又は市が指定する研修を修了した者で適任と認めた者を、本人の申し出により防災リーダーとして認定し名簿に登録する制度。
- 防災指導員
- 防災リーダーとして名簿に登録された者のうちから、「まちづくり協議会又は自治会等」からの推薦に基づき、地区ごとに1人を防災指導員に委嘱する制度。
防災関係施設・設備・システム等
緊急情報伝達手段
- 同報系防災行政無線
- 市が、屋外拡声スピーカーや戸別受信機を介して、住民等に対して迅速・正確に防災情報を伝えるシステム。
- 屋外に設置しているスピーカーから放送され、携帯電話等を持たない方でも情報を取得することができる一方、住宅の気密性向上等により屋内では音が聞こえにくい状況があるため、鳥取市では鳥取市防災アプリ等の複数の情報伝達で補完している。
- また、災害時の設備の被災等で、スマホやインターネットが使えなくなった場合にも放送が可能であるほか、鳥取市の整備する屋外拡声スピーカーにはすべてバッテリーを搭載しており、停電時にも放送が可能であるなど耐災害性の高い無線設備。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1368147898446/
- 鳥取市防災アプリ
- 鳥取市が発信した緊急情報を防災行政無線と同時に文字と音声で自動配信し、平時には防災学習ツールとして利用可能なスマートフォン向け防災用アプリケーション。
- 情報取得困難者(聴覚に障がいのある方や外国人旅行客など)に対して迅速かつ正確に情報を発信し、かつ、デジタル化する時代に即応できる新たな緊急情報伝達手段の拡充を目的とする。
- スマートフォンがマナーモードでも緊急時には文字と音声で通知を行う緊急プッシュ通知機能や、カメラに映る風景に災害発生イメージを重ねて表示して身近な危険を視覚的に体感する災害体験AR機能、ドイツ語やフランス語など9言語に対応している。
- また、災害時の避難タイミングをあらかじめ市民自ら学びながら計画作成するマイタイムライン機能や、避難所などで日本語での会話が困難な方との意思疎通を行えるようコミュニケーションボード機能など、随時改善を行っている。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1654656122380/index.html
- 鳥取市防災ラジオ
- 災害時などに鳥取市が緊急情報を発信した際、ラジオ局(FM鳥取)の電波を利用して、自動で起動するラジオ。
- 防災行政無線で発信する緊急情報を放送し、平常時は一般のラジオとして使用可能(FM/AM可)
- また、放送を聞き逃した時など、自動録音された緊急情報を再生できる。
- 市が原価の約8割を負担して、委託契約を締結した市内の小売事業者が、市費負担を差し引いた販売価格で委託販売している。
- 販売価格:2,000円(税込)※市費負担分減額後の価格
- FM鳥取緊急割込み放送
- 鳥取市が緊急情報を発信する場合、FM鳥取の放送に強制的に割り込んで放送を行うシステム。
- FM鳥取株式会社
- コミュニティFM局。鳥取市の防災局としての機能を有する。通称:RADIO BIRD(82.5MHz)
- 鳥取市防災ポータルサイト
- 本ウェブサイト。鳥取市の防災に関する情報を集約・構成した防災専用ウェブサイトであり、避難情報の発令エリアやハザードマップなどを地図上で表示することができる。
- 予報から観測情報までの様々な情報・リンクを掲載し「ここさえ見れば」様々な防災情報にアクセスでき、幅広く市民に利用いただけることが期待できるほか、事前インストール等の必要が無いウェブブラウザで動作することから、災害ボランティアや行政の応援者など本市が被災した場合に的確な支援を受けるための受援目的での効果も期待している。
- 鳥取市公式LINE
- 鳥取市の公式LINEアカウント。イベント情報やゴミ出し日を教えてくれる機能などがある。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1670225256632/index.html
- 全国瞬時警報システム:J-ALERT
- 弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を携帯電話等に配信される緊急速報メール、市町村防災行政無線等により、国から住民まで瞬時に伝達するシステム。
- https://www.fdma.go.jp/about/organization/post-18.html
- Lアラート:災害情報共有システム
- 災害発生時に、地方公共団体等が、放送局・アプリ事業者等の多様なメディアを通じて地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ効率的に伝達する共通基盤。
- https://www.fmmc.or.jp/commons/
避難場所・避難所等
- 支え愛避難所(ささえあいひなんじょ)
- 町内会の集会所等、住民が自主的に設ける避難のための施設(鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例第2条第1項第9号に定める施設をいう。)※ただし、市町村が安全性などの面で「支え愛避難所」として適当と認めない避難所を設定する地区は、対象外。
- https://www.tottori-wel.or.jp/system/site/upload/live/35/atc_1523633562.pdf
- 自主避難所
- 台風が鳥取市に接近する恐れがある場合や、梅雨前線等で市域に長時間降雨が予想され、洪水や土砂災害等の発生が懸念される場合に、不安を感じ自主的に避難を希望される市民の方の受け入れ先を確保することを目的に開設する避難所。
- https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1627439265890/index.html
- 指定緊急避難場所(屋内)
- 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるときに、一時的に避難して身の安全を確保するための緊急避難場所のうち、「洪水・土砂災害・地震・津波・大規模な火災」の災害の種類ごとに、市があらかじめ指定する屋内の施設。
- 指定緊急避難場所(屋外)
- 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるときに、一時的に避難して身の安全を確保するための緊急避難場所のうち、「洪水・土砂災害・地震・津波・大規模な火災」の災害の種類ごとに、市があらかじめ指定する屋外の場所。
- 指定避難所
- 自宅が被災して帰宅できない場合などに、被災者が一定期間宿泊・滞在する避難所のうち、市があらかじめ指定する施設。
- 福祉避難所
- 避難所での生活が必要となった方のうち、要配慮者等(高齢者や障がいのある方等)で、避難所での生活に特別な配慮を必要とする方が滞在する施設。
- 協定避難所
- 鳥取市と企業等が締結した協定の内容に基づき、市民の避難に利用できる市有外の施設や場所。
施設
- 鳥取市防災備蓄倉庫
- 鳥取市が市役所本庁舎に隣接して建設した物資拠点。自ら必要な物資等の調達が困難な被災者を支援するため、避難所等で必要となる物資や資機材等を備蓄している。
- 治水ダム
- ダムに入ってくる水の一部を一時的にダムに貯め込んで下流に流れる量を減らし、洪水による被害を最小になるような役割を持つダム。
- https://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/about_us/qanda/q4_answer.html
- 利水ダム
- 川の水をダムに貯めてその水を生活用水(水道水)、工業用水、農業用水などに利用したり、また、その水を高いところから落とすことにより、水車(タービン)をまわし発電したりする役割を持つダム。
- 多目的ダム
- 治水ダムと利水ダムの2つの役割をかねそなえたダム。
- 砂防堰堤(さぼうえんてい):砂防ダム
- 土石流など上流から流れ出る有害な土砂を受け止め、貯まった土砂を少しずつ流すことにより下流に流れる土砂の量を調節する施設。
- 雨水ポンプ場
- 排水できなくなった雨水をポンプで汲み上げて強制的に河川へ放流する役割があるポンプ場。
- 排水機場
- 台風などで水門を閉鎖した時、内水域の水位が降雨や下水排水により上昇した場合、排水機場のポンプを運転して内水域の水位を下げる施設。
- 広域防災拠点
- 広域的な災害対策活動が円滑かつ効率的に行われる、様々な活動の拠点。
- 津波避難ビル
- 津波が発生したとき、又は、発生のおそれがあるときに市民等が津波から避難できる一時的な避難場所使用を想定した施設。
設備
- マンホールトイレ
- 下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保するもの。
- 災害トイレ
- 下水道管路に直結していない災害時に運用する想定の仮設トイレ設備について、本ウェブサイトのハザードマップ上で表示するため鳥取市が独自に定義した単語。
- 応急給水栓
- 震災時から復旧までの間、周辺地域の皆さんに飲料水を供給するため整備された水栓。
- https://www.water.tottori.tottori.jp/1840.htm
- 自動体外式除細動器:AED
- 心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器。
災害対策関係法律
基本法関係
災害予防関係
- 河川法
- 海岸法
- 砂防法
- 森林法
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 地震防災対策特別措置法
- 建築基準法
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律
- 津波対策の推進に関する法律
- 津波防災地域づくりに関する法律
- 気象業務法
- 避難情報に関するガイドライン
災害応急対策関係
- 消防法
- 水防法
- 災害救助法
- 被災者生活再建支援法
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
- 地震保険に関する法律
- 災害弔慰金の支給等に関する法律
国土強靭化
鳥取県の防災関係制度
条例
- 鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例
- 鳥取県危機管理のための対策本部に関する条例
計画

- 共に命を守る最善の行動を。
- 鳥取市役所
- 危機管理部 危機管理課
- 電話番号:0857-30-8033